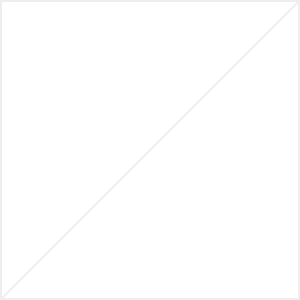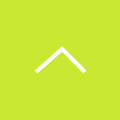Ver.9
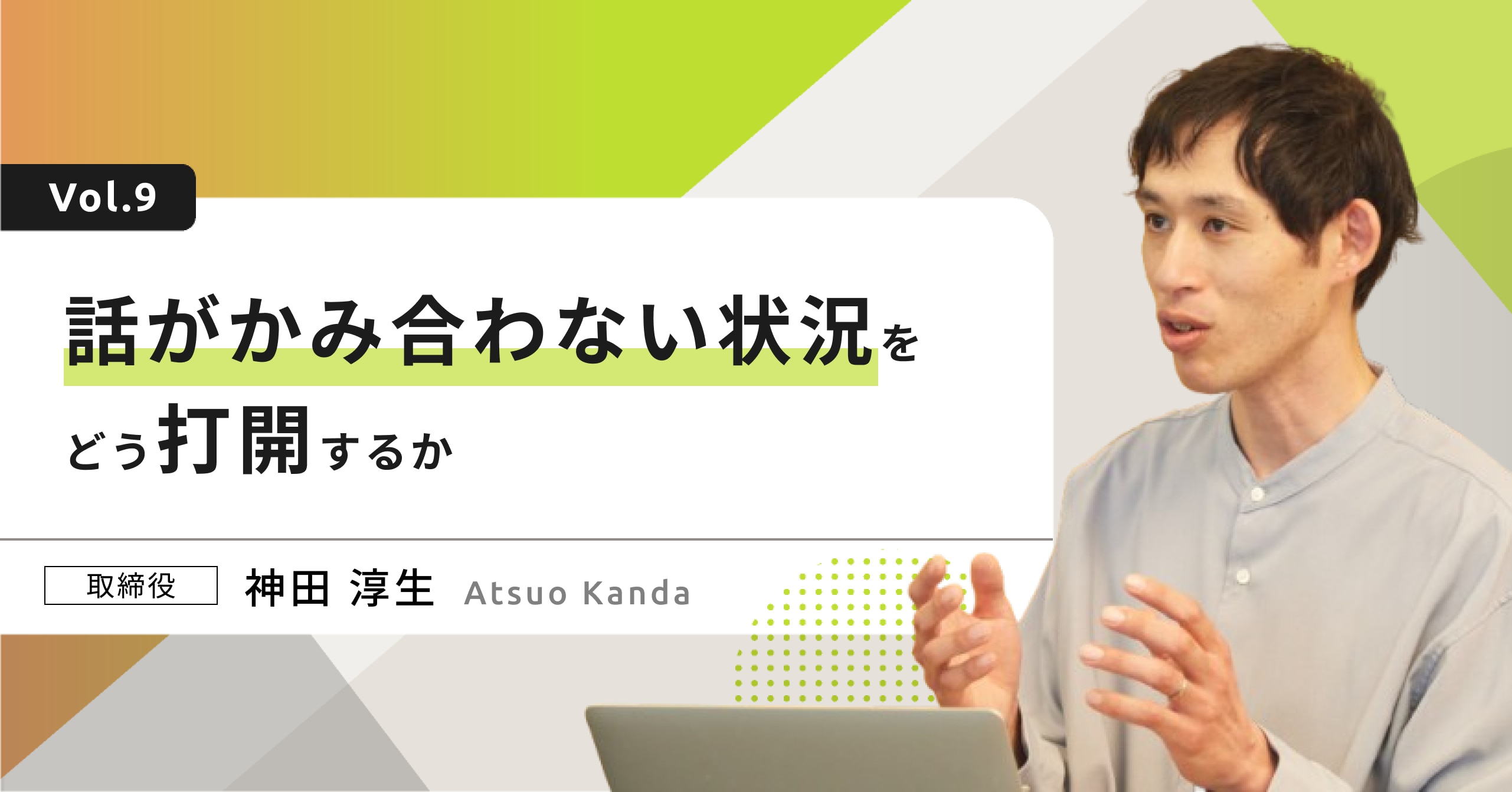
“この記事はポッドキャストの内容を編集しています。
記事をもっと楽しみたい方はぜひポッドキャストをお聞きください”
▼本記事の話者プロフィール
神田 淳生(かんだ・あつお)取締役
🎓 経歴・略歴
関西学院大学 総合政策学部 卒業(2003‑2007)
卒業後、デジタルエージェンシーにWebデザイナーとして入社
2008年:株式会社アジケにウェブデザイナーとしてジョイン
2015年:マネージャー就任
2018年:UXデザイン事業部取締役に昇格
2022年:デザイン組織開発支援事業部の取締役に就任
💡 スキル・専門領域
UI/UXデザイン:ブランドサイト、Web・アプリ設計のプロジェクトリード多数
組織向けデザイン支援:組織内のデザイン体制構築、人材育成プログラム『Dods』開発
デザインシステム構築:大手金融機関向けにデザインシステム導入をリード
今回のテーマは「話がかみ合わない状況をどう打開するか」。
プロジェクトの進行において、クライアントやチームメンバーと話がかみ合わず、意図した方向に進まないといった経験は誰しもあるのではないでしょうか?
今回は取締役の神田さんに、その打開策と円滑なコミュニケーションのために必要なポイントを語っていただきました。
――話がかみ合わない要因とは?
新規プロジェクトの開始時には、クライアントの性格や業界の特性をまだ十分に理解できていないため、意思疎通が難しくなることがよくあります。最近も新しいプロジェクトが始まりましたが、スタート時点で少し苦労しました。
その原因として、大きく2つの要因があると考えています。
1. 用語のズレ
業界や職種が異なると、同じ言葉でも意味が微妙に異なる場合があります。
例えば、『ボリューム』。デザイナーにとっての『ボリューム』はデザインの密度や情報量を指しますが、マーケターにとっては市場規模やプロジェクトの規模を意味したりしますよね。そういったことが、クライアントと会話を重ねるうちに起きるんです。
プロジェクトの途中で『あれ? 意味がズレてる?』と。専門用語が多い業界だと特に注意が必要です。
2. イメージのズレ
言葉だけでアウトプットの方向性を伝えるのは難しく、思い描いているものがズレてしまうことがあります。
例えば、デザインの要件を決めるときに、『シンプルなデザイン』という表現を使ったとします。でも、クライアントにとっての『シンプル』と、デザイナーにとっての『シンプル』は違うことがあります。
視覚的なイメージ、具体的なビジュアルやサンプルを共有することがすごく重要になります。
――話がかみ合わない状況を打開する方法は?
話がかみ合わない状況を解決するには、コミュニケーションの質と量を意識的に高めることが重要です。
1. コミュニケーションの質を高める
コミュニケーションの質を高めるには、相手との関係性を深め、より自然なやり取りができるようにすることがポイントです。
人間関係のレベルには段階があります。
- 挨拶を交わすレベル
- 業務以外の話ができるレベル
- 冗談を言い合えるレベル
この段階を意識して関係を深めることで、より円滑なコミュニケーションができるようになります。私は円滑なコミュニケーションを素早く成り立たせるために、対面での会話を強く薦めています。
リモートワークが主流になりつつありますが、直接会うことで得られる情報量は圧倒的に多いです。可能なら、一度は対面で話す機会を作ることが、関係性の構築には欠かせません。
2. コミュニケーションの量を増やす
プロジェクト初期は、特に頻繁なコミュニケーションが必要です。
週1回の定例会議だけでは情報共有が足りないので、最初のうちは週2~3回、短時間のミーティングを設けるのが理想です。短時間の雑談でも、相手の考え方や価値観が見えてくるので、非常に有効だと考えています。
また、メールよりもチャットツールを活用することで、素早いレスポンスが可能になります。また、メールだと堅苦しくなりがちですが、チャットなら『これってどういう意味ですか?』と気軽に聞けたりします。誤解を早めに解消できるので、プロジェクトの進行がスムーズになります。ぜひチャットツールの導入も検討してみてください。
3. 相手の言葉を使って共通言語を作る
『オウム返し』がすごく役に立ちます。相手の言葉をそのまま使うことで、相手にとって馴染みのある表現で伝えることができます。
例えば、
相手:「この修正の分量、多めですけど、大丈夫ですか?」
神田:「この修正の分量、多めですが、大丈夫です。」
このように、意識的に相手の言葉を拾っていくことで、ズレを最小限にする狙いがあります。
また、相手の知識量だったり、あるいはその人の性格とか文化に近い単語を知っていくことで、業界やプロジェクトの理解度がぐんと高まります。
――最後に
話が噛み合わないということはお互いがお互いのことを間違えて認識しているということで、結局は自分も相手の言葉を間違って解釈しているということなんです。
相手との会話の合計時間中、自分の方が長く話した時は、失敗のコミュニケーションだと私は考えています。
相手の考えをどこまで聞き出せるか、引き出せるかが『話が噛み合う』の第一歩ですから。
“この記事はポッドキャストの内容を編集しています。
記事をもっと楽しみたい方はぜひポッドキャストをお聞きください”