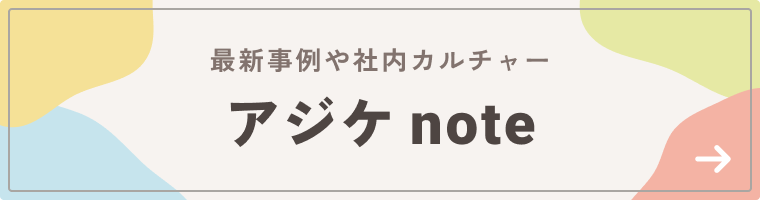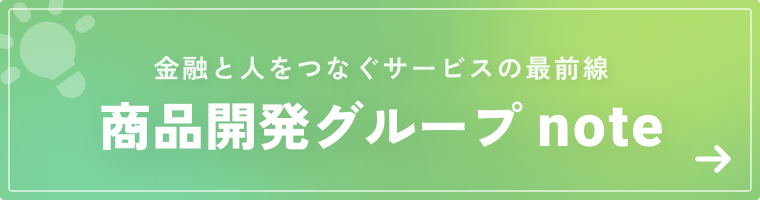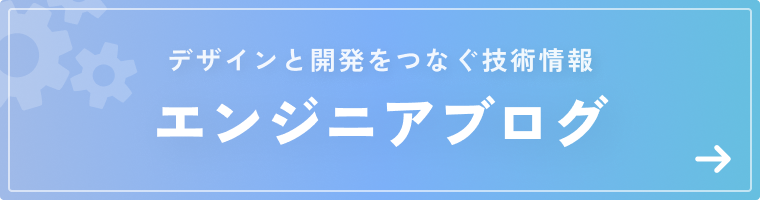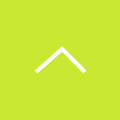銀行のデジタル化 〜銀行を「使いやすい機関」にするためには〜
「銀行ってなんか遅れてる」、「最近はデジタル化して老人には難しくなってしまった」銀行に対するイメージは様々。なんとなく遅れているイメージを持っている人もいれば、早い進歩についていけない人もいます。
この記事では銀行は実際どこまでデジタル化が進んでいるのか、銀行をよりたくさんの人に「使いやすい機関」として認識されるためにはどんな工夫が必要なのか、今後の展望などをまとめてみました。
目次[非表示]
- 1.デジタル化の背景
- 2.事例
- 2.1.SMBCグループ
- 2.2.三井住友銀行「Olive」
- 2.3.ふくおかフィナンシャルグループ
- 2.4.みんなの銀行
- 3.現状の課題
- 3.1.幅広いユーザー特性においてのユーザビリティの向上
- 3.2.IT人材、デザイン人材の確保
- 3.3.システムの統合の難しさ
- 4.今後の展望
- 4.1.さらなる顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)の向上
- 4.2.セキュリティの確保
- 4.3.デジタルプラットフォーム化
デジタル化の背景
利用者の利便性向上
銀行のデジタル化の始まりは1960年代に登場した「ATM」といわれています。ATMの普及により銀行の改革が進み、1980年代にインターネットを用いた「オンラインバンキング」が登場しました。
1980年代はインターネットの一般普及が急速に広まっていた時期でもあり、同時にオンラインバンキングの利用者も急増しました。ですが、この時期のオンラインバンキングというものはただ一方的に銀行がお客さんにサービスを提供するだけのもの。2008年のリーマンショックを筆頭に、金融の不満が爆発し、多くの金融人材がICT業界に流出したと言われています。同時期にIPhoneが登場し、瞬く間にスマートフォンは大衆化されたものとなりました。大衆化されたスマートフォンを活用し、デジタルテクノロジーは銀行のビジネスモデルに変革をもたらしました。
それまで銀行の取引を行うためには、「特定の場所」と「規定の時間帯」に「出向く」必要がありましたが、今や「その場」で「いつでも」利用できるようになったのです。
業務効率化
UIはユーザーが触れる部分の設計が主な役割であるのに対し、UXは商品・サービスの認知から購入、廃棄に至るまでの一連の流れを設計するというものです。
Webサイトやアプリケーションの場合は、商品・サービスを利用することで得られる楽しさや心地よさなどがUXに当たります。
単純な機能性だけではなく、商品・サービス購入後のカスタマーサポートや対応などがユーザー体験に影響します。
事例
利用者にとって銀行のサービスや商品への親和性が進むにつれて銀行業界の競争は激しくなっています。利用者が求めるサービスのレベルは日々高くなっていき、 銀行もそうしたニーズに応えようとあらゆる革新を起こしています。どんな革新を起こしているのか、いくつか事例をみてみましょう。
SMBCグループ

SMBCグループはあらゆる事業領域で顧客の利便性向上を目的とし、テクノロジーを活用した新規サービスの創造や既存サービスの進化を行ってきています。
2015年にはFGのイノベーション創出をミッションとして担う、ITイノベーション推進部を設置したほか、2020年4月にはデジタルソリューション本部を設置(デジタル戦略部及び法人デジタルソリューション本部)し、他行に先駆けて銀行のデジタル化を進めています。
特に、デジタル化に対して抵抗のある人々に対しても「使いやすい」銀行として位置付けるために、「UI(ユーザインターフェース)/UX(ユーザー体験)」に注力しています。
ホームページ・アプリ・インターネットバンキングだけではなく、対面サービスの際に利用する端末「SMBCタブレット」は利用者からも「使いやすい」と好評で、2021年度にはその親和性と評価の高さから「グッドデザイン賞」を受賞しました。
三井住友銀行「Olive」
 2023年3月からスタートした三井住友銀行が提供する「Olive」。「Olive」はモバイル総合金融サービスとしてアカウント一つで三井住友銀行の口座、クレジット、デビット、ポイント払い、さらには保険・証券まで管理できる便利なサービスです。
2023年3月からスタートした三井住友銀行が提供する「Olive」。「Olive」はモバイル総合金融サービスとしてアカウント一つで三井住友銀行の口座、クレジット、デビット、ポイント払い、さらには保険・証券まで管理できる便利なサービスです。
今まで各サービスを利用するためにはそれぞれのアカウントを開設して、専用のアプリをダウンロードして使用しなければならないという手間がありましたが、その手間は省くことでサービスを利用する利用者の利便性の向上と同時に、「利用しやすいサービス」としてブランドイメージを位置付けることができました。
ふくおかフィナンシャルグループ

地方銀行もデジタル化に取り組んでいる事例はたくさんあります。
ふくおかフィナンシャルグループでは2019年4月から明確にDX(デジタルトランスフォーメーション)を基本方針の一つに掲げ、様々な金融商品取引の電子化や完全非対面のみんなの銀行などで注目されてきました(みんなの銀行については下別途説明します)。
自社内も業務プロセス再構築としてデジタル技術を活用した抜本的な業務見直しをしており、ペーパーレス化、印鑑レス、バックレス化などで約2割の効率化を実現し、その削減された人員・ 時間・空間などのリソースを捻出して「コア事業の磨き上げ」や「新しい取組みへのチャレンジ」に取り組んできました。
みんなの銀行

「みんなの銀行」は既存の銀行機能をオンライン化したインターネットバンキングとは一線を画す、国内初のデジタルバンクです。
口座開設から ATM 入出金、振込など、全てのサービスがスマートフォン上で完結できるデジタル起点の新しいサービスを提供しています。
現状の課題
銀行のデジタル化において、様々な面から利用者と銀行にメリットがあると述べましたが、様々な課題も同時に発生しています。代表的なものをいくつか確認してみましょう。
幅広いユーザー特性においてのユーザビリティの向上
銀行のデジタル化において最も重要な課題の一つは、誰もが使いやすいユーザビリティを実現することです。
特に、高齢者やデジタルに不慣れな人、ハンディキャップを持った人などどんな人でも気持ちよく利用できるサービスを提供するためには、ユーザーリサーチやユーザビリティテストを反復的に繰り返しながら日々ユーザビリティを向上させていくことが必要です。
IT人材、デザイン人材の確保
銀行のデジタル化に重要な役割を果たす従業員は、システム開発やデータ解析、セキュリティ対策などの技術的なスキルが求められます。
また顧客体験をデザインしていくデザイン人材の確保も必要です。しかし、それらのスキルを持った人材確保の難しさや体制づくりの難しさから、デジタル化の遂行が困難なケースが多く見受けられます。
システムの統合の難しさ
銀行のデジタル化には、現存する複数のシステムを統合するという大きな課題もあります。顧客データなどの情報は複数のシステムに分散して保存されている場合が多く、情報の一元化のためにはシステムの統合が不可避なケースがあります。
加えて、銀行内部の業務プロセスの変革や改善が必要になるため、大きな労力が必要とされます。
今後の展望
このように、急速に進む銀行においてのデジタル化。上記の内容を踏まえ、今後の展望をまとめてみました。
さらなる顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)の向上
銀行は今後、より優れた顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)を提供することが求められます。そのためには、自動化やIoT、ビッグデータなどのテクノロジーを「顧客目線」でサービスに取り入れていくことが重要です。
ただ闇雲にデジタル化するのではなく、顧客にとって本当に使いやすく、またこれまでにない新しい体験やスムーズな体験を提供できる銀行が差別化に成功していくと考えられます。
セキュリティの確保
銀行において一番の課題は、セキュリティの確保です。顧客情報や資金移動などに関する情報は最も重要であり、その漏洩や不正アクセスは深刻な問題となります。
したがって、銀行は日々変化するセキュリティリスクに迅速かつ適切に対応するためのシステムやツールの開発・導入が必要です。
デジタルプラットフォーム化
金融業界においては、オンラインバンキングやモバイルバンキング・スマートフォンアプリなどを提供することを指します。これらのデジタルプラットフォームを駆使し、顧客が手軽に自分たちの銀行口座を管理できるようにすることが求められています。
今後はAIを活用した顧客サポート、ブロックチェーン技術を活用したセキュリティの向上など、技術の進化が期待されます。
顧客にとって、より手軽かつ安心して銀行業務を行えるような環境が整うことが期待されるということです。
参考資料:
データ戦略の推進状況、金融界要望の主な方針案、注目されるインターネット・バンキング戦略、SMBCグループ、三井住友銀行Olive、ふくおかフィナンシャルグループ、みんなの銀行