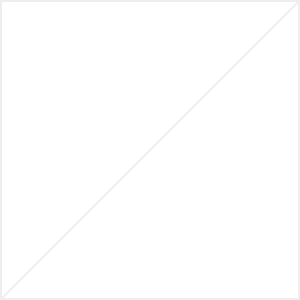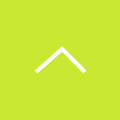Ver.12
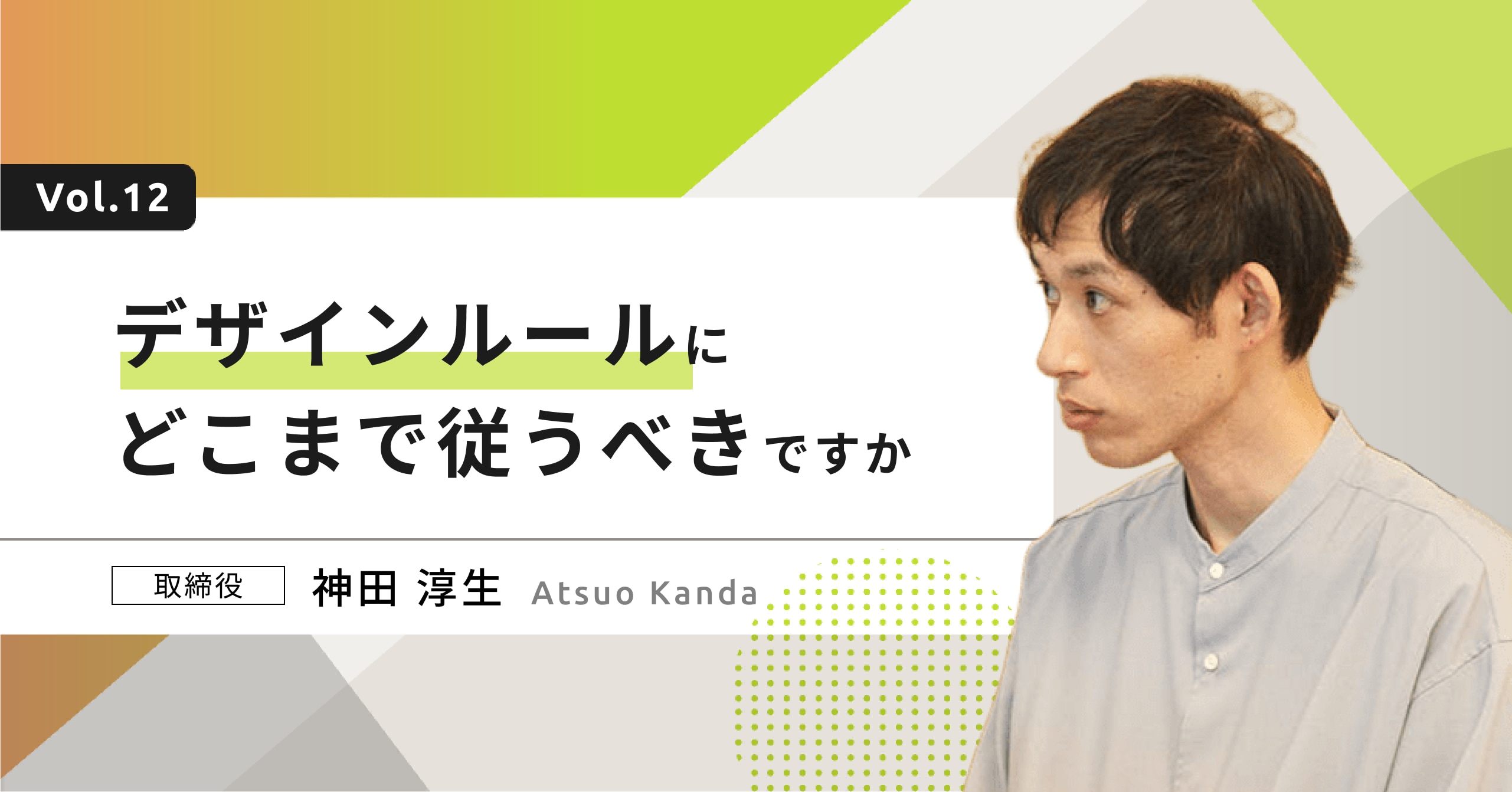
“この記事はポッドキャストの内容を編集しています。
記事をもっと楽しみたい方はぜひポッドキャストをお聞きください”
▼本記事の話者プロフィール
神田 淳生(かんだ・あつお)取締役
🎓 経歴・略歴
関西学院大学 総合政策学部 卒業(2003‑2007)
卒業後、デジタルエージェンシーにWebデザイナーとして入社
2008年:株式会社アジケにウェブデザイナーとしてジョイン
2015年:マネージャー就任
2018年:UXデザイン事業部取締役に昇格
2022年:デザイン組織開発支援事業部の取締役に就任
💡 スキル・専門領域
UI/UXデザイン:ブランドサイト、Web・アプリ設計のプロジェクトリード多数
組織向けデザイン支援:組織内のデザイン体制構築、人材育成プログラム『Dods』開発
デザインシステム構築:大手金融機関向けにデザインシステム導入をリード
デザインルールやスタイルガイドに従っているのに、現場ではなぜかうまくいかない——そんな悩みを抱えていませんか?
本記事では「デザインルールにどこまで従うべきか?」というテーマで、実際のプロジェクト現場で起きている課題とその解決策を深掘りします。
デザインシステムやスタイルガイドが形骸化しないためのコツ、ルール作成時の注意点、チーム全体での運用方法などを語っていただきました。
デザインルールは「守るもの」か「活用するもの」か?
スタイルガイドやデザインシステムは、見た目や操作性を統一し、品質を保つための重要なルールです。
しかし、あまりに厳密すぎたり、古くなったルールに縛られすぎると、現場では「デザインの自由度が奪われている」と感じてしまうことも。
そこで出てくるのが、「このルール、本当に今のプロジェクトに合ってるの?」という疑問です。
デザインガイドライン作成時のポイント(作る側の視点)
ルールを作る側が持つべき観点として、以下の3点のポイントを抑えてみてください。
① ルールはスリムに保つ
ガチガチに作り込みすぎると、想定外の事象に対応できず、例外対応が増える。結果、ルールが守られなくなってしまいます。
② 常に最新化する(同時に古いルールを捨てる)
ルールは生き物。新しいものを追加するだけでなく、使われていない・古いルールは定期的に削除することで、使いやすさが維持されます。
③ 余白(裁量)を残す
各プロジェクトの特性に合わせて柔軟に対応できるよう、ルールにはある程度の「余白」を設けておくことが重要です。
デザインルールを使う側の視点(現場の運用)
現場のデザイナーが意識すべきなのは、ルールを「守ること」ではなく「活用すること」。
- まずはガイドラインの中でベストを尽くす
- それで難しい場合は、関係者と相談しながら柔軟に対応する
- デザインルールは目的ではなく手段。プロジェクトの成功が最優先
「ルールを守る側」と「作る側」が連携しながら、最適解を探ることが大切です。
デザインシステムを浸透させる方法
せっかく作ったデザインシステムが活用されない——これは多くの企業が抱える課題です。仕組みの中に強制力を組み込むことが大切なんです。
例えば、承認フローに組み込む。
デザインシステムの準拠チェックを、リリース前の最終承認ステップに入れることで、運用の中に自然と組み込むことができます。
ルールを「運用フローに組み込む」ことで、形骸化を防ぐのです。
まとめると?
Q. デザインルールは絶対に守るべきですか?
A. 必ずしも絶対ではありません。ガイドライン内でベストを尽くし、難しい場合は関係者と相談して柔軟に対応しましょう。
Q. デザインシステムが形骸化してしまいました。どうすれば?
A. 運用フローに強制力を持たせたり、ユースケースを追加することで再活性化を図りましょう。
Q. スタイルガイドが複雑すぎて活用しにくいです。改善方法は?
A. スリム化し、古いルールを整理・削除することで、使いやすさを取り戻すことができます。
ユースケースの活用で、ルールを「使える」ものにする
ガイドラインだけでは抽象度が高くて若手が使いこなせないという課題もあります。
そこで必要なのが「ユースケースの提示」です。
例:
- キャンペーンサイトなら>このコンポーネント
- プロダクト紹介ページなら>この構成
など、用途に応じた“使い方の例”を示すことで、ルールの活用が一気に進みます。
本来のデザインの楽しさ・クリエイティビティを忘れずに
絶対に忘れてはいけないということは、ルールに従いすぎて面白みのないデザインになってはならないということ。
ガイドラインを守ることは大切ですが、それ以上に「誰のために、何のためにデザインするのか」を常に問い直すことが、より良いデザインにつながります。
- ルールの枠内で創造する力
- 見る人の心を動かす「遊び心」
デザインルールは目的ではなく、手段
デザインルールに正解はありません。ですが、「誰のために・何のために作るのか」という原点に立ち返ることで、きっと今よりよいルール運用ができるはずです。
- デザインルールは「守るもの」ではなく「活用するもの」
- 作る側と使う側の対話とアップデートが鍵
- スリム化・最新化・ユースケースの導入で形骸化を防ぐ
関連記事
こちらの記事もぜひ合わせてお読みください📕
お問い合わせはこちら
アジケでは、金融機関・大手企業のデザインルール設計や運用支援を多数手がけています。
デザインシステムやガイドラインにお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください!